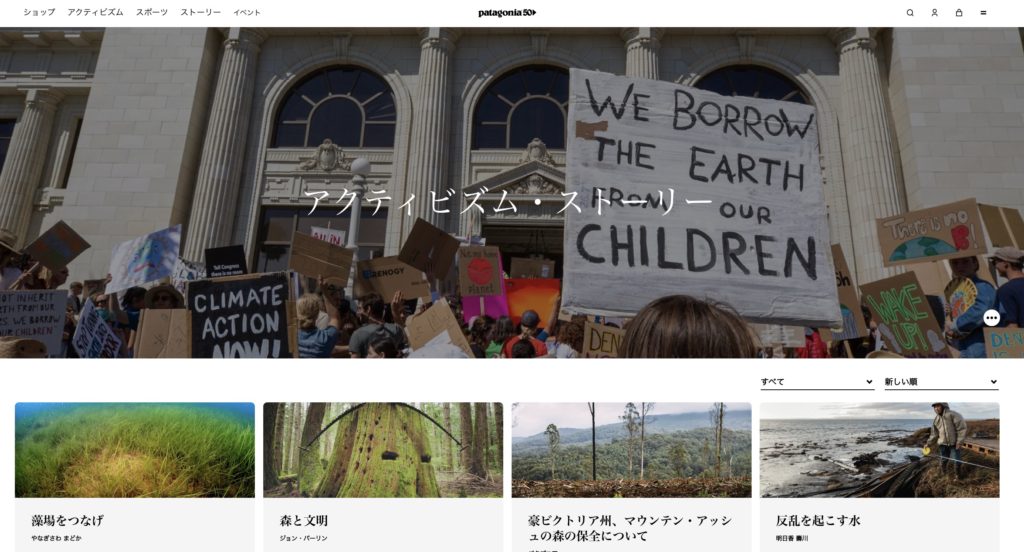熱海へ取材に行きました。
東海道線の沿線(藤沢)に生まれ育った者として、ついつい神奈川県だと思ってしまう、わりと身近な感覚の熱海。
しかし最近の私は、ずいぶん山とか田畑で過ごす時間が多く、果たして朝イチに到着してそのまますぐに熱海のバイブスに馴染めるのだろうか…?と心配になり、結局、前日から単身、熱海入りすることにしました。
想像以上に観光客で賑わっていることに驚きながらも、少し静かなあたりまで歩いて神社にご挨拶し、ローカルな温泉に浸かり、地元の人が通う定食屋さんでイカフライを食べ、翌朝は早くから海辺で瞑想するなど、自分自身を熱海にどっぷりsink inさせてから取材に向かいました。結果、気持ちの上でも大正解だったと思います。

今回の取材先は、あの枝廣淳子さんが代表の「未来創造部」さん、テーマは「ブルーカーボン」です。
少なからず環境活動に携わってきた一人として、憧れのアカデミアである枝廣さん。現在は熱海を拠点に、ブルーカーボンに関する取り組みを積極的に展開されています。
ブルーカーボンとは
ブルーカーボンとは、海草の藻場やマングローブといった海洋生態系がCO2の吸収源になることを指します。近年、CO2の吸収量をクレジット化して経済力に変えることもできるようになりました。
かねてよりCO2を蓄えるための木の植樹は行われてきましたが、空気のない水中では海洋植物本体に加えて海底土壌にもCO2を固定することができ、実際、地上の生態系よりも最大10倍ものCO2が貯えられるそうです。可能性が感じられますね。
枝廣さんの本がとてもわかりやすいので、ご興味のある方は記事と合わせてぜひご覧ください。
個人的にこの取材で印象的だったことは(文字量の都合で記事には書けませんでしたが)、枝廣さんと一緒に会社を運営する光村さんが、30年以上も熱海で活動する中で、漁師さんとの信頼関係に最も配慮し、マリーナ建設などの際にも漁師さんと一緒に活動できる道を選んだお話など。
光村さんの努力のおかげで藻場のフィールドワークが実現でき、フィールドがあるからこそ藻場を学びに熱海に訪れる人も増える。漁業権のある日本では、他の海辺で同じことをしようとしても、なかなかすぐにはうまくいかないことも多いのです。熱海では光村さんによる信頼貯金があるおかげで、教育と観光という、ブルーカーボンの2つの可能性が開きつつありました。
記事の掲載先
今回は初の寄稿先となる、パタゴニア社のアクティビズム・ストーリーです。いつも読むたびにインスパイアされていたページの制作に参画できるとは、大変貴重な機会に恵まれて、とても光栄です。
ほとんどの記事を拝読し、どれも活動としての意義や情熱の高さ、志の大きさなどに頭がさがる思いで胸がいっぱいになりました。こうした人々の気持ちに寄り添い、サポートを続けるパタゴニアは、やっぱりどうしてもかっこいい。パタゴニアだけに頼ってる場合じゃないと分かってはいるけど、でもやっぱりすごいと思います。
同社に勤める竹内てっちゃん、実は数年前に出会っていたご担当の明石さん、アクティビズムの活動をスーパーバイズされている中西さんに、大変お世話になりました。またご一緒できる機会に恵まれることを楽しみにしています。
最後に、枝廣さんたちが立ち上げたブルーカーボンネットワークでは、個人または団体で登録できるサポーター制度があります。世界が注目するブルーカーボンについて見識を深め、熱海に定期的に通いやすくなる絶好の機会として、わたしもサポーターになりました。気になる方はぜひご一緒しましょう。
(記事はこちら↓)
パタゴニア アクティビズム・ストーリー
投稿者プロフィール
-
柳澤 円(やなぎさわまどか)
ライター/コピーライティング/翻訳マネジメント
社会課題と暮らしのつながりを取材し、複数媒体にて執筆。主な関心領域は食・農・環境・ジェンダー・デモクラシー・映画。企業の制作物なども実績多数。
10代からの留学を含む海外生活後、都内のコンサルタント企業でナショナルクライアントの発信を担当。多忙ながら充実の日々は2011年3月に東日本大震災を経験したことで一変、兼ねてより願っていた自然に近い暮らしへと段階的にシフトする。神奈川県内の中山間地へ移り、フリーランスライターを経て2019年、夫・史樹と共に株式会社TwoDoors設立、代表就任。取材執筆のかたわらで自家菜園と季節の手仕事など、環境負荷の少ない暮らしを実践する。書き手として、心の機微に気づく感性でい続けることを願い、愛猫の名はきび。